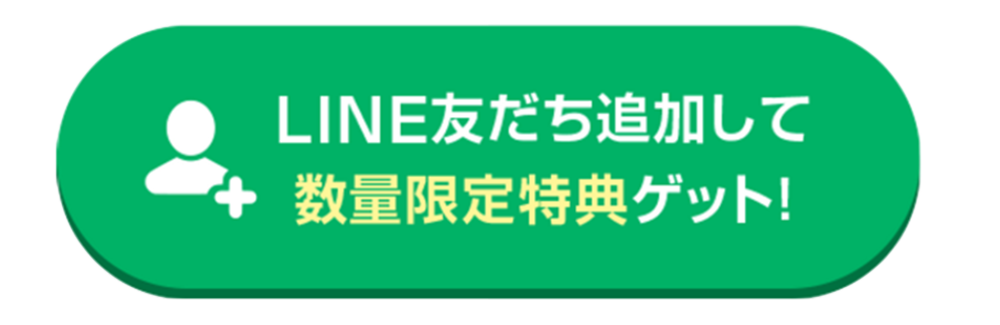一生の間に食べるご飯の量はおよそ8万杯。
1日3食、80年間食べ続けたとして、
人が一生のうちに食べるご飯は、お茶碗8万杯分もあるそうです。
そう思いながらも現実は、
冷凍ご飯をチンして食べる、炊飯器で少量だけご飯を炊く。
どこか少し、味気ない食卓。
忙しい日々に追われ、そんな生活を送っている方は
現代社会において少なくないはず。
私もその一人でした。

いつかの料亭で食べたあの土鍋ご飯。
土鍋ご飯が炊けたときの匂い、
蓋を開けるときの高揚感。
そして一口食べてわかる、格別の美味しさ。

あの美味しさは知っているけれど、
土鍋ご飯は火加減が難しくて目を離せない。
土鍋でご飯を炊く毎日に憧れるけれど
土鍋ご飯は火加減が難しくて目を離せない。
そんな土鍋ご飯がもっと簡単にできたら、
例えば電子レンジで簡単に炊けたら、
毎日でも簡単に美味しいご飯を食べられるかも。
そんな思いを叶えるため、今回この企画を立ち上げました。
前回のプロジェクトでは、1599人、総額1631万円の支援をいただきました!

生産量が限られる商品のため、増産は難しく、
お待たせしてしまっている、たくさんのお客様にはご迷惑をおかけしております。
とは言え、前回のプロジェクトで購入できなかった方からの問合せも多くいただいておりますので再度、募集プロジェクトを実施いたします。

「電子レンジで炊くご飯って本当に美味しいの?」
実は疑問に感じていました。
ただ、それなりに「美味しい」ではなく、
自信を持って「美味しい!」
と言えるものでないと、お客さまの元へお届けできない。
この土鍋の開発で一番大切にしたのは
なによりも「ご飯の美味しさ」です。
電子レンジで簡単に炊ける容器はあるけれど
ご飯が美味しく炊け、できる限りの手間を省いた
本格的なご飯炊き土鍋はあまりありませんでした。
私たちが譲れない、「美味しさ」を求めて、
三重県にある老舗陶器問屋との開発が始まりました。

佐治陶器は大正12年創業の歴史ある陶器問屋。
ご飯炊き土鍋をはじめ、一般用から業務用まで数々の土鍋を扱っている
言わば土鍋のプロフェッショナルです。
「レンジで炊ける美味しいご飯土鍋を作りたい。」
その思いを実現するために、佐治陶器の佐治社長とともに何度も打ち合わせを重ね、企画を練りました。
そして信頼のおける作り手として紹介してもらったのが、
「伊賀焼」の窯元でした。

伊賀流忍者の発祥地として有名な三重県伊賀市。
そこで作られる「伊賀焼」は1300年続く国指定の伝統工芸品として知られています。
すぐさま伊賀へ行き、窯元の職人秋野さんに伊賀焼についてお話を伺いました。
「伊賀焼きの土は息をするんです。
だからご飯炊き土鍋に、そしてレンジ炊きにも非常に適している。」

話を伺ううちに
レンジ炊き土鍋を作るなら伊賀焼しかない!
という思いがますます募りました。
ご飯土鍋に詳しく、目利きのプロである佐治社長、
土鍋作り40年の職人、秋野さん。
お二人の力を借り理想の土鍋を完成させるため、長い時間と多くの試行錯誤を重ねました。
美味しく炊くために、土鍋の構造をどう工夫するか、
吹きこぼれにくくするためには?高さや形状はどうするのか。
数々の問題に直面しながらも、土鍋作りに奮闘しました。
そして、
思い描いていた以上の
レンジ炊き土鍋が誕生しました。



伊賀の土には、400万年前に生息した生物や植物の名残があります。
そこで採掘した陶土は高温で焼き締めるとその名残が燃え尽き、小さな穴が沢山あいたスポンジ状になります。
その小さな穴が熱を保ち、水分を調整する役割を担うため、
伊賀土は「息をする」と言われています。
「伊賀焼」はレンジ炊きご飯土鍋にぴったりだったんです。

伊賀の土には、400万年前に生息した生物や植物の名残があります。
そこで採掘した陶土は高温で焼き締めるとその名残が燃え尽き、小さな穴が沢山あいたスポンジ状になります。
それほど伊賀土は特別な性質を持っています
日本で採れた土の特長を存分に活かした伊賀焼土鍋は、優れた調理道具として、プロの料理人からも支持されています。


レンジ炊きで、さらに短時間で美味しく炊き上げるためには、
お米の芯までムラなく熱が伝わることが大切です。
底から上層へ対流が生まれると熱が均一に伝わり、
一粒一粒がふっくらと膨らみ美味しく炊きあがります。
この対流をしっかりと作るために、土鍋の内側は丸みを帯びた形状に仕上げました。

また、ご飯炊きには土鍋の高さも非常に重要です。
高さをつくることでお米がよく踊り熱が均一に通るため、甘さをより際立てます。
美味しいご飯をつくる条件と、一般的なレンジに入るサイズを考え、最適な高さを打ち立てました。

伊賀の息をする土と対流構造で作られた、伊賀ノ匠で炊くご飯。
1粒1粒が立ち、しっかりと食感を感じられます。

ひとくち噛めば、甘みがじゅわり。
口の中にお米本来の旨さが溶け出します。
お米本来の旨みを感じていただきたいので、
ひとくち目はそのまま食べてみてください。
きっと違いがわかるはずです。
レンジで炊けるのは白米だけではありません。
玄米、雑穀米も炊けます。

健康に気をつかう方に人気の玄米や雑穀米も簡単に炊けます。
粒立ちごはんを楽しめるから、おにぎりや、卵かけご飯も美味しい。
レンジ炊きでも、炊き込みご飯まで作れます。





今回、直火で炊いた土鍋ご飯と、伊賀ノ匠で炊いたレンジ土鍋ご飯の味を比較するため、お米の粘り・硬さ・外観などを総合的に評価する「食味鑑定値」の測定を依頼しました。
食味鑑定値とは、お米に含まれる成分の含有量を測定し、美味しさを総合的に評価するもの。お米生産者の間で美味しさの指標のひとつとして利用されています。
結果、市販土鍋を用いた直火炊飯のご飯より高い数値が出ました。

食味値の結果はあくまでも参考値ですが、
レンジ炊きでも美味しいということがわかる、嬉しい結果に。
さらに、伊賀ノ匠専用のレシピを考案していただいた料理家の山本さんにも感想をいただきました。


自分専用の土鍋ご飯って特別感がありますよね。
伊賀ノ匠は0.5合〜1合までのおひとりさまサイズ。自分だけの土鍋として楽しめます。
炊飯器で少量のご飯を炊くと、炊きムラができてしまいあまり美味しく仕上がらないこともありますが、伊賀ノ匠なら0.5合からでも美味しいご飯が炊けます。

少し食べたいときのちょっと炊きも良し。
温め直しても美味しいから、多めに炊いて保存も良し。
好みに応じてお使い分けください。
炊飯器で少量のご飯を炊くと、炊きムラができてしまいあまり美味しく仕上がらないこともありますが、伊賀ノ匠なら0.5合からでも美味しいご飯が炊けます。
硬めさの好みが分かれる場合や
食べたいお米の種類が違うときにも
「私は柔らかめが好きだけど、家族は硬めが好き」という方や、
「夫は白米派、私は玄米派」という方にも伊賀ノ匠をぜひ使っていただきたいと思っています。
硬さが違うご飯も、種類が違うお米も、
伊賀ノ匠を2つ使い分けて炊いていただ
炊飯器を併用して、同時に炊いていただく。
そうすることで炊き立てのご飯をご家族と一緒に食べられます。

火を使うのが億劫な方に
レンジなら安心して使っていただける
レンジ炊きだから、手間をかけず美味しいご飯を食べたい方にはもちろん、
土鍋ごはんを炊きたいけど、火を使うのが億劫に感じる方や
焦がしてしまわないか不安‥という方にも安心して使っていただけます。
一人暮らしのお子さまやご年配のご両親への贈り物としてもおすすめです。
※レンジの性能に合わせてお好みの加減に調整ください



1. 吹きこぼれにくい構造
伊賀ノ匠は縁を高くすることで吹きこぼれにくい構造を目指しました。

2. おひつとしても使える
お米の水分を調整してくれる伊賀焼土鍋はおひつとしても使えます。
冷蔵保存してレンジで温めなおすと水分をほどよく含み、炊き立てのようなふっくらとした仕上がりに。

3. 焦げ付かず洗いやすい
直火でのご飯炊きは、火加減が肝心。
調整に失敗すると土鍋を焦がしてしまうこともあります。
その焦げ付きが厄介なのは、普通に洗ってもなかなか取れず、次に炊いた時、焦げ癖がつき味も変わってしまうところ。
土鍋の焦げ落としは浸け置きしたり、重曹を使ったりと手間と労力がかかります。

伊賀ノ匠はレンジで炊くため、面倒な焦げ落としは必要なし。
炊きすぎてしまっても焦げ付かず、お米のこびりつきも洗剤でするっと落とせます。

「土鍋は焦げ付きが面倒‥」と感じていた方にレンジ炊きはおすすめです。
4. 軽々持てて、扱いやすいサイズ
伊賀ノ匠は約850gと軽量。りんご3個分の軽さです。
保温性を保つために、土鍋には十分な厚みが必要。
ですが、レンジ炊きにはおいては火の通りが良くなるよう薄すぎず、厚すぎずの絶妙な加減が必要でした。
そして毎日使っていただけるよう、軽々と持てる重さが理想でもありました。

5. 本体と蓋のみで洗い物が少ない
企画を練り始めた当初、たくさんのレンジ炊き容器を調べる中で感じていたのは、
「内蓋やトレーなどのパーツが多くて洗い物が大変そう」ということ。
伊賀ノ匠は蓋と本体のみのシンプルな作りで、洗い物がたった2つだけ。
形状も洗いやすく、極力手間を省きたい方にぴったりなんです。

そのままお茶碗としても使えばさらに洗い物を減らせます。
6. 水量目盛り付きでわかりやすい
毎日の使い勝手を考えて土鍋では珍しい、0.5合と1合の水量目盛りを入れました。
軽量カップでわざわざ測る手間がかかりません。


設計段階では、「いつもの食卓に寄り添う温かみあるデザイン」を模索しました。
シンプル且つ、黒一色の潔さ。
土の風合いを生かした表情と、手ざわり。
手作りの温かさも相まって、土鍋の趣がしっかりと感じられます。


底の素地部分は土そのものの質感を残しました。
何度もやり直して辿り着いた絶妙なバランス。
見えるところに置いても素敵な佇まいです。


伊賀といえば誰もが一度は耳にしたことがある、伊賀流忍者の発祥地。
山々に囲まれた自然豊かな場所です。
伊賀焼の起源は遥か奈良時代、伊賀の地には豊かな陶土が存在し、陶器作りに適した環境が整っていました。

江戸時代中期には身分の高い京都のお公家さんが温かく美味しいご飯を食べるため、当時では珍しい、火にかけても割れない伊賀土を使った土鍋を作らせました。
その後伊賀焼はご飯炊き土鍋の生産地として知られるようになり、その技術が現代へ継承され高く評価されています。

伊賀ノ匠が作られる窯元は3代目の秋野さんご夫婦、二人三脚で営まれています。

土本来の良さを大切に、土鍋を作り続けて40年。
「何回やっていても焼き上がりが心配。窯を開け上手く焼き上がった土鍋を見ることが毎回嬉しいし、苦労が報われる気持ちになる」と語ってくれた秋野さん。
数えきれないほど土鍋を作り続けてもなお、一つ一つに思いを込め、ひたむきに土鍋作りと向き合い続けています。

蒸気穴をあけたり、「伊賀」の印を押す作業は奥さまの手作業で行われます。

伊賀ノ匠は秋野さんご夫婦の手で丁寧に作られるため、どうしても1ヶ月に1000個までしか作れません。
発送までお待ちいただくこともあるかと思いますが、応援いただいたサポーター様の元へお届けする期間、楽しみにお待ちいただければ幸いです。

開発担当者の辰宮と申します。
このプロジェクト立ち上げの経緯を少しお話しさせてください。
仕事がある平日は忙しく、食事はできるだけ簡単に済ませてしまう生活。
冷凍ご飯をストックしたり、スーパーでパックご飯を買ったり・・
そんな食生活にどこか違和感を感じていました。
そんなとき、料亭で土鍋ご飯を食べる機会があり、その美味しさに思わず感動!
「土鍋で炊くご飯ってこんなに美味しかったっけ?」と衝撃を受けました。
そのとき思ったんです。
「時短できるもの」「便利なもの」で溢れる世の中。
でも本当の喜びは心を豊かにしてくれる「美味しさ」にあるはず。

そう思うのと同時に、
自分のようなめんどくさがりでも続けられる、美味しいご飯炊き土鍋を作ってみたい!という気持ちがふつふつと湧いてきました。
後日、思い切って会社に開発を提案。
何件もの陶器屋、窯元へお声がけし、佐治陶器にたどり着いたことで無事に企画が通り、伊賀ノ匠のプロジェクトが開始。
窯元の職人、秋野さんに納得して製作していただくため、佐治社長と試行錯誤し、設計を詰めていきました。
何度も壁にぶつかりながら、やっとの思いでお披露目することができたのは、一丸となって協力していただいた佐治社長や秋野さんのおかげです。


「伊賀焼」に出会い、土鍋の美味しさに加え「伊賀焼の素晴らしさをもっと多くの人に知ってもらいたい」という思いも強くなりました。
一つ一つ職人の手によって作られる伝統的な伊賀焼を、ご家庭でぜひ気軽に取り入れていただきたい。
そして、お仕事や子育てで日々忙しくされている方に、美味しいご飯を食べる喜びを届けたい。
レンジ炊き土鍋の手軽さと美味しさを、ぜひこの伊賀ノ匠でご賞味ください。


・サイズ(約):幅14.5cmx高さ14cm
・重さ(約):850g
・材質:陶器
伊賀の地で採掘した土を使うため伊賀ノ匠は100%日本製です。
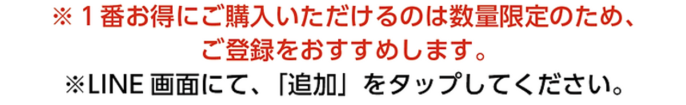
※開発中のため、仕様が変更になる可能性があります。